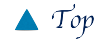🔍 初心者のためのやさしい古事記
多くの人は『日本神話』をきちんと読んだことがないと思います。 せいぜい、子どもの頃にチロッと『児童文学』でかじったことがあるくらいで、とワクワクしながら読むと……ギリシャ神話とか、旧約聖書の創世記(アダムとイブ)みたいなお話なのかな?
・ 雲の上から海をかき混ぜて『おのころ島』を作った? ・ 伊邪那岐神が禊ぎをしたら、顔から3神が生まれた?という、予想外の展開に、いろんな意味で驚かされる。 「なんか想像してたのと違う」とは思いながらも、「でも自分の国の神話だから」と我慢しながら読み進めると、今度は、黄泉の国でゾンビに追いかけ回されるホラー展開となり…… 「いくら、昔の人が作った物語とはいえ、これはちょっと……」 となって、あえなく挫折。 ・ ・ だいたいこんな感じなのですよね。誰に話を聞いても。 それ以来『古事記』に触れてこなかった方は、当HPで『古事記』の分析記事を読んでも、そもそも『古事記』の内容、全体の流れそのものの知識がないと思います。 ですので、 このエリアでは、まずは『古事記』ってナニ? って方のために ダイジェスト版として全体の流れと、簡単な解説をしていきます。 ・ ・🎓 神話時代の古代日本 のイメージ
【かんたんな古事記の流れ】・ ・ ここから、『古事記』の本文となります。昔々、イザナギ様とイザナミ様という神様が、高天原の神様(カムロギ・カムロミ)の命を受けて地上に降り、『天の浮橋』から天の日矛で『おのころ島』をはじめとする大地を作りました。 この島で、彼らは夫婦となったのですが、多くの島々や神々を生み出したときに、火の神のヤケドで妻は亡くなってしまいました。 黄泉の国(死者の国)へと旅立った妻を追って、イザナギ様も黄泉の国へ行きますが、ゾンビに追いかけられ、地上に逃げ帰ります。 戻ったイザナギ様は、川で禊ぎ(身を清める)を行いました。 場所は、筑紫地方の日向国・小戸の阿波岐原です。 この禊ぎのときに、彼の身から3人の神々が生まれました。左目から太陽神。右目から月神。鼻から荒神です。
【原文】『古事記』(序)
古事記上卷 幷序 臣安萬侶言 夫 混元既凝 氣象未效 無名無爲 誰知其形 然 乾坤初分 參神作造化之首 陰陽斯開 二靈爲群品之祖 所以 出入幽顯……
 |
うぎょ〜っ! 般若心経? どこの国の言葉ですか? |
🔍 古事記序文 (はじめに)
( ⇲ 新ウインドウで『古事記』本格的な訳へのLINKあり)
『古事記』(序文)
「従正五位上」官位 太 安万侶 (奈良時代)
これより、天皇の命令を受け、この書をまとめた 太安万侶 が、この『古事記』の序文を書かせていただきますわ! ・ ・ 昔々…… この世界の始まりの頃は、全てが混沌としていて、何もカタチがなかったそうですわ。 見えない、聞こえない、感じ取れない……。 無ではない。しかし、とらえどころもない。 なんと言いましょう? 名前がなく、形もなく、何がどうなっているのか誰にも分からない状態だったそうですわ。 でも、宇宙が形を成し始め… 天地(霊界と物質界)が分かれ… そして、神々がこの世(物質界)を創造すると、そこで陰と陽が生まれ、世界は『渦』となって、そこから万物の現象が生まれたのでした。 『渦』がすべてを生み出したのです。 そして、地上の神々もまた、この世に降り立ち、姿を現されました。 このようにして、この世界は形成され、神々や人々の時代が始まりました。 各地では神々がこの世界を守り、貴族や豪族も繁栄を築きました。 日本の歴史は、神が国を治め、民を導き、文化を築き上げました。 これが、『平城の都』が栄える現在(奈良時代)よりはるか昔におこった出来事だったわけですが、時の天皇がワタシに次のように仰せになりました。 【陛下のお言葉】
これにて、ワタクシ 太安万侶 は、陛下より直々に編纂の命を賜ったのですわ。
そこで私は 稗田阿礼 という聡明な人物にも、各土地に伝わる口伝を語ってもらいながら、それを記録することになりました。
ワタクシ 太安万侶 は、は阿礼の語りを書き留めただけではなく、古い書物とも見比べながら、書を記録してまいりました。
古代の言葉はシンプルで、語彙力に乏しく、現代の言葉(奈良時代)に訳すのは困難ではございましたが、できる限り忠実に記録するよう努めました。
この『古事記』の記録は、『神代時代』から小治田大宮の推古天皇の治世までが書かれていて、三巻に分けて天皇陛下に献上しました。
ワタクシ 太安万侶 は、この重大な任務を果たし、今、この序文を書いております。心から恐れ多く思っております。
和銅五年正月二十八日、太安万侶
これより、天皇の命令を受け、この書をまとめた 太安万侶 が、この『古事記』の序文を書かせていただきますわ! ・ ・ 昔々…… この世界の始まりの頃は、全てが混沌としていて、何もカタチがなかったそうですわ。 見えない、聞こえない、感じ取れない……。 無ではない。しかし、とらえどころもない。 なんと言いましょう? 名前がなく、形もなく、何がどうなっているのか誰にも分からない状態だったそうですわ。 でも、宇宙が形を成し始め… 天地(霊界と物質界)が分かれ… そして、神々がこの世(物質界)を創造すると、そこで陰と陽が生まれ、世界は『渦』となって、そこから万物の現象が生まれたのでした。 『渦』がすべてを生み出したのです。 そして、地上の神々もまた、この世に降り立ち、姿を現されました。 このようにして、この世界は形成され、神々や人々の時代が始まりました。 各地では神々がこの世界を守り、貴族や豪族も繁栄を築きました。 日本の歴史は、神が国を治め、民を導き、文化を築き上げました。 これが、『平城の都』が栄える現在(奈良時代)よりはるか昔におこった出来事だったわけですが、時の天皇がワタシに次のように仰せになりました。 【陛下のお言葉】
「これまでまとめられた、『帝記』や『旧辞』やけどな、ウチも読んだんやけど虚偽の英雄伝説ばかりで全然アカンかったわ〜。各地の口伝伝承も、同じ話でも人によって内容バラバラやん。何がホントかようわからん。今、これを正さな、ホンマのこと分からんなってまうわ。せやろ?」
📓 『古事記』が作られた動機は、天皇の思いつき
元々『古事記』が作られた動機は、元明天皇の思いつきだった。「ウチな、ご先祖様のこと、どんなんやったか知りたい思てんねんけど、『帝記』読んでみたらな、もうめっちゃ適当なことばっか書いてあってビビったわ。あんなん、どう考えても違うやろ? で、朝廷によう出入りしてはる人の中に、マロっちゃん (太安万侶) って奴がおってん。そんで、ちょっとお遣い頼んでみたんや。どんな話が出てくるか、めっちゃ楽しみやわ。ワクワク!」
 初心者が楽しく読める古事記入門1−天地創造
初心者が楽しく読める古事記入門1−天地創造